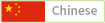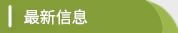- 首页>
- 最新信息
2016.04.21
「互連網+」という言葉、聞いたことはありますか?
中国で「インターネット+(中国語:互聯網+)」がバズワードになっています。古くは、易観国際(Analysys International:中国のインターネットシンクタンク)が提唱した概念ですが、最近ではテンセントのポニー・マーが上海市に対して「”インターネット+”を動力に、経済社会のクリエイティブな発展を推進」と題してプレゼンテーションを行い、注目を集めました。
この「インターネット+」という概念、何かというとインターネット産業がオンライン領域(ネット広告、オンラインゲーム等のインターネット上で完結していたサービス)に留まらず、オフライン領域(O2OやIoT)への領域に進出し、生活のあらゆるところでインターネットが利用される、「インターネットの次の姿」を称して使われています。
インターネットバンキングや電子マネー決済など、インターネット産業の既存産業への進出は今に始まったことではありませんが、中国にとって大きな転換点はPCからモバイル端末の時代に入ったことでした。
PCが主流の時代は、我々はインターネットを文字通り「使って」いました。インターネットに繋がるには、まずPCを立ち上げ、接続し、入力することによって情報を得ていました。一方、モバイル時代にはインターネットを「使う」のではなく「そこにある」という状態に変わります。それは、スマホを常に持ち歩いているというレベルから、ウェアラブルで常にビッグデータが収集され、手振り身振りで家電を操作できるIoTの領域まで幅広くイノベーションが生まれます。メッセンジャーサービスの変遷が代表的ではないでしょうか。MSN MessengerもQQも「オンライン」「オフライン」「離席中」と設定を変えられたのに、LINEやWeChatにはありません。常に「オンライン」だからです。
中国では、上海市で公共料金の支払やビザ手続き等の行政サービスがWeChatで提供されるようになりました。
インターネットで先んじているアメリカや日本ではなく、中国で次世代のインターネットサービスが普及しつつあるというのは興味深い現象です。既存産業に食い込むには必ず既得権益との衝突があります。既に地ならしがされたエスタブリッシュメントな先進国より、荒地からキャッチアップする方がイノベーションが起きやすいのでしょうか。いずれにせよ、日本もこれに刺激を受けてほしいと思います。